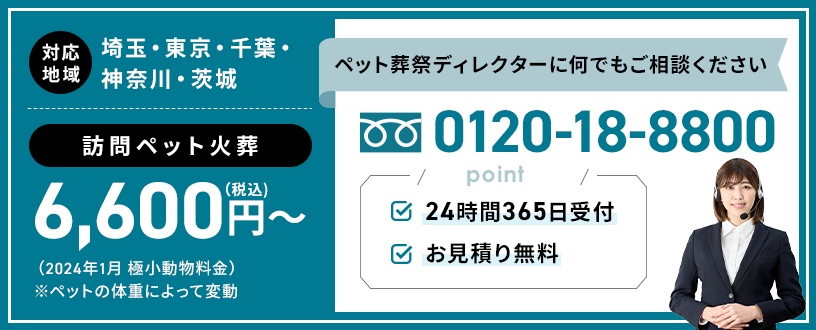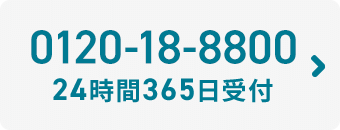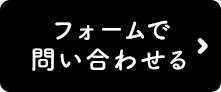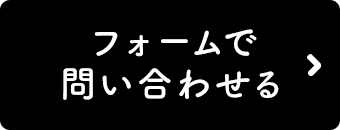犬と暮らす飼い主様のなかには、クッシング症候群という病気を耳にしたことがある方がいるかもしれません。病名だけは知っているが、どのような病気なのかわからないという方も多いでしょう。
クッシング症候群は、内分泌疾患のひとつで高齢犬に多いと言われています。今回の記事では、犬のクッシング症候群の概要や原因、余命などを解説します。また、動物病院での検査内容、治療法、費用の目安などについてもご紹介します。
目次
犬のクッシング症候群の概要や余命
はじめにクッシング症候群の概要や発症しやすい犬の特徴、余命についてお伝えします。
一度発症すると完治が難しい病気
クッシング症候群は、犬の内分泌疾患として比較的多い病気で、猫ではまれな病気です。
「副腎皮質機能亢進症」(ふくじんひしつきのうこうしんしょう)とも呼ばれ、副腎皮質ホルモンであるコルチゾールが過剰に分泌されることで発症します。
クッシング症候群は、何かひとつの症状があらわれるわけではなく、コルチゾールが徐々に体に悪影響をおよぼしさまざまな症状を呈します。
この病気は、自然に発症する場合と、他の病気の治療で用いるステロイド剤の長期使用で発症する場合があります。前者の場合は完治が難しく生涯つきあう必要のある病気だと言えます。
発症しやすい犬の種類や特徴
プードル、ボストンテリア、ダックスフンド、ビーグルなどの犬種に特に多い言われることもありますが、どの犬種でも発症する可能性があります。特に8歳以上の中高齢の犬で比較的多く、性別には関係なく発症します。
余命について
2020年にイギリスで行われた研究結果によると、クッシング症候群の診断を受けたあと、治療を行なった場合の中央生存期間が521日だったのに対し、無治療の場合の中央生存期間は178日だったそうです。
犬の年齢や他の基礎疾患などの要因も関連しますが、できるだけ早期発見早期治療がその後の余命に関わる病気だと言えます。
犬がクッシング症候群になる原因とは
クッシング症候群の原因としては、大きく自然発症とステロイド薬の影響に分けられます。さらに自然発症の場合、下垂体性のものと副腎性のものが挙げられます。
下垂体腫瘍
犬では下垂体が原因となる下垂体依存性のクッシング症候群が最も多く、およそ9割を占めると言われています。なかでも下垂体の腫瘍が原因となって発症することが一番多いと言えます。
病態は、下垂体という脳の底の部分からぶら下がる小さな内分泌器官から「副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)」が過剰に放出されることで副腎が刺激され、その結果コルチゾールの分泌も増加してしまうというものです。
副腎腫瘍
副腎腫瘍など、副腎自体が原因となってコルチゾールが過剰に分泌されて発症することもあります。全体の1割程度とそれほど多い原因ではありませんが、雌犬に発症が多いという傾向があります。
薬の長期投与
ステロイド薬は慢性の炎症や免疫に関する病気で用いられる薬です。コルチゾールはステロイドホルモンのひとつなので、ステロイド薬を高用量で長期間使用すると、医原性のクッシング症候群になる可能性があります。
犬のクッシング症候群の症状

クッシング症候群は、さまざまな症状が出るため、この症状がみられたら必ずクッシング症候群だと言えるわけではありません。
ここでは、クッシング症候群の初期段階でみられる代表的な症状と末期段階でみられる代表的な症状にわけて解説します。
おもな初期症状
犬のクッシング症候群の症状として最も代表的なものが、異常にたくさん水を飲んで尿を大量にする「多飲多尿」です。また、水をがぶがぶ飲むだけでなく、食欲が異常に旺盛になります。
クッシング症候群の場合、犬の外貌に変化がみられることも多いです。一般的な見た目の変化としては、お腹だけが異常に目立つ「腹部膨満」や、肥満、皮膚や被毛の変化が顕著です。
特に、皮膚が薄くなったり弾性を失い、ちょっとした傷が治りにくくなったり、毛を刈ったあとに発毛しなくなることがあります。また、体にかゆみを伴わない脱毛がみられることが多く、体全体に左右対称に脱毛するのが一般的です。
初期の段階で治療をはじめると、これらの症状が緩和されその後の生活の質を落とさずに比較的長いあいだ病気をコントロールすることが可能なので、これらの症状がみられる場合は早めに動物病院を受診すると良いでしょう。
おもな末期症状
体への悪影響が継続すると、糖尿病や膵炎、高血圧などを併発するようになり、命にかかわる症状が出はじめます。筋力も低下するため、階段が上がれなくなったり、ジャンプができなくなったり、すぐに息切れするようになることもあります。
最終的には全く歩けなくなってしまうこともあります。クッシング症候群では血栓ができやすくなるため、最悪の場合は血栓が太い血管に詰まって突然死する可能性もあります。
これらの症状が出はじめる末期の段階では、クッシング症候群の治療は大変難しいと言えます。手遅れにならないうちに、早期発見早期治療を心がけるようにしましょう。
動物病院での犬のクッシング症候群の検査と治療

犬のクッシング症候群の診断にはさまざまな検査が必要です。ここでは、検査内容や治療法などをお伝えします。また、治療費に関しては犬の状態や動物病院によって差がありますが、おおよその目安についてご紹介します。
検査内容
クッシング症候群が疑われる場合には、臨床症状の聞き取りや、ホルモン検査を含む血液検査、画像検査などを行って総合的に判断します。
特に、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)を犬の体に投与して、副腎からのコルチゾール分泌量を調べる「ACTH刺激試験」というホルモン検査は診断に欠かせません。
同時に、従来の血液検査で血糖値、コレステロール値、肝臓などの数値を確認します。また、CT、MRIなどの画像診断で下垂体や副腎に形態学的な異常がないかどうかを確認することも必要です。
治療法と治療費の目安
治療法は原因によって異なります。ステロイド薬の過剰投与による発症の場合、薬を徐々に減らすことで対応します。ステロイド薬は突然やめてしまうと体に悪影響を及ぼすことが多いため、自己判断せず獣医師の指示に従いましょう。
下垂体性や副腎性のクッシング症候群の場合、内科的治療と外科的治療があり、多くのケースでは内科的治療が選択されます。
この場合、コルチゾールの分泌を抑制する薬を生涯に渡って飲み続けることになります。薬の量によっては副腎皮質機能が低下し過ぎて「副腎皮質機能低下症」になることがあるため、適切な薬の量がわかるまで定期的な検査を受けることになります。
外科的な治療では、手術によって下垂体や副腎を腫瘍ごと摘出します。手術にはリスクが伴ううえに、術後もホルモン補充のために一生薬が必要になるため、現在の日本ではあまり選択されることはありません。下垂体腫瘍に対しては、腫瘍がそれ以上大きくならないように放射線治療を行うこともあります。
治療費は、手術や放射線治療の場合、数十万円単位で必要となることが多いです。手術後も比較的高価なホルモン薬を一生必要とします。内科的な治療の場合も、薬代のほかに定期的な検査代などが必要となるために、月に数万円~10万円程度が必要となるケースが多いと言えます。
早期発見早期治療が愛犬の余命を握る鍵
今回の記事ではクッシング症候群について、原因や検査法、治療などをお伝えしました。下垂体性や副腎性のクッシング症候群に関しては予防方法がありません。早期発見早期治療がその後の愛犬の余命に関わります。飲水量や尿量の確認をはじめ、愛犬の日々の様子をしっかり観察し記録しておけば、クッシング症候群だけでなく、さまざまな病気の早期発見にもつながりますよ。